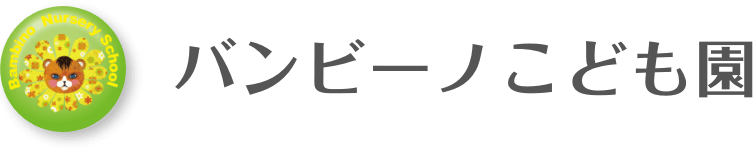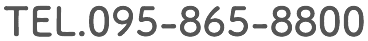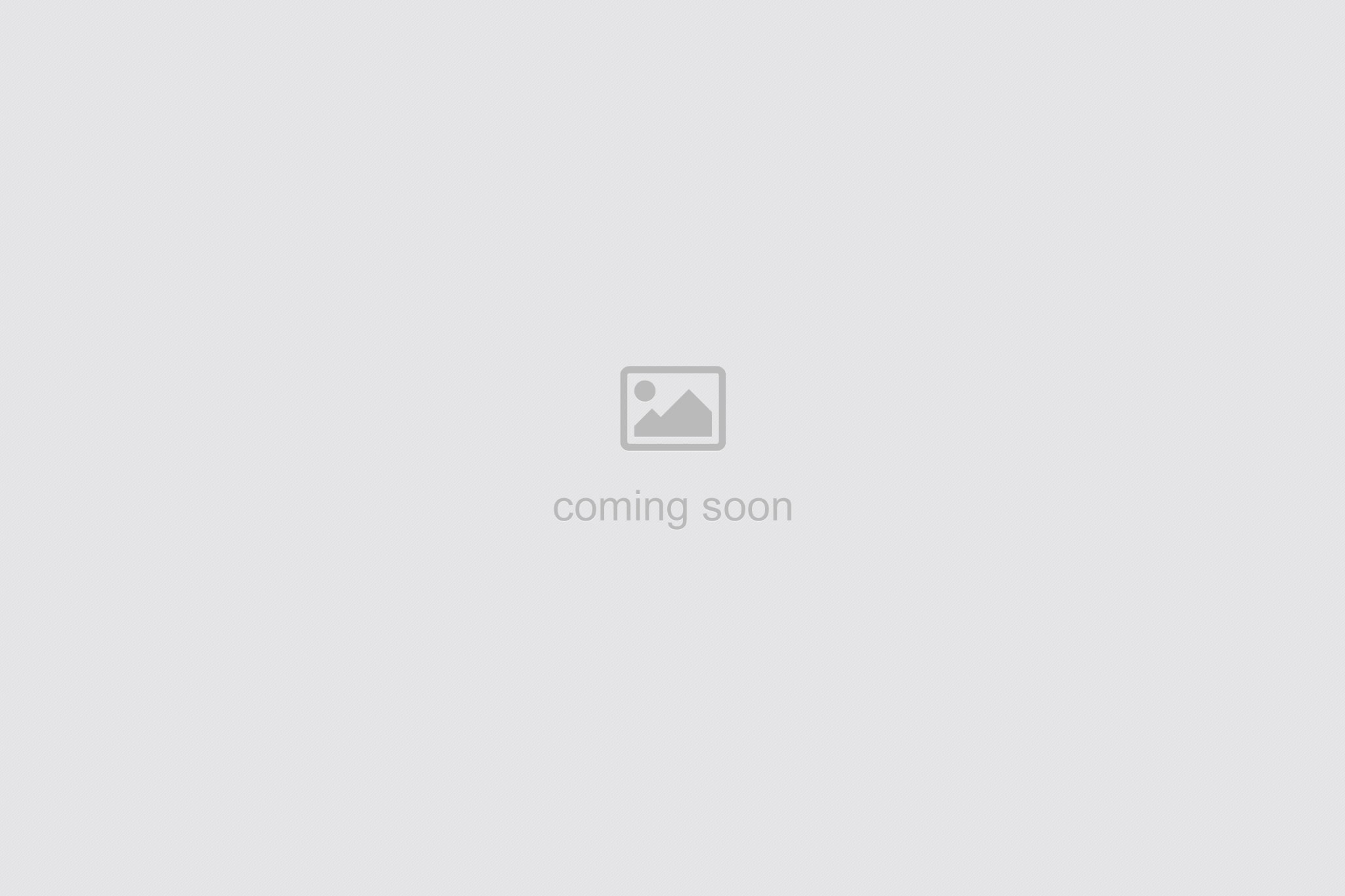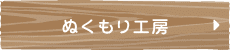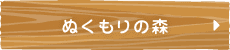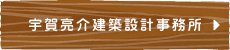えいご
“きっかけ”のひとつとして・・・
世界の国々と対等に生きていく為に英語は必要です。他国ではバイリンガル・トリリンガルは普通の事です。何故なら、他国と陸続きの国々ではいくつもの種類の言葉が交わされるのが日常だからです。その点、日本は島国で、良くも悪くも母国語のみの習得しか必要ではありませんでした。ようやく小学校中学年からの英語教育が必須となりますが、日本語には無い英語の発音は自然に習得するにはなかなか難しい年齢に入ってしまいます。勿論、大人になってから英語を習得した方もたくさんいらっしゃいますが、かなりの努力によるものでしょう。その努力を重ねる時間を、この幼児期に楽しく与える事によって、いわゆる「英語耳」を身に付け将来きっと役に立つと思うのです。
レッスン風景(未満児)
レッスン風景(以上児)
そのほか・・・ 絵本の読み聞かせ
フォニックス
異文化を知る
年長クラスで英語レッスンの成果を確認できます
10月の英語の絵本が届きました♪
10月の英語の絵本が届きました♪
おでかけ
たべる
からだをうごかす
運動あそび
リズムあそび
かんがえる
制作あそび
 季節の制作をすることで、行事や習わしを体感します
季節の制作をすることで、行事や習わしを体感します ハサミなど道具の正しい使い方を覚え、巧緻性や構築力を養います
ハサミなど道具の正しい使い方を覚え、巧緻性や構築力を養います絵本
 言葉で表現する力や感動する心、想像力や思考力、好奇心を育てます
言葉で表現する力や感動する心、想像力や思考力、好奇心を育てます 言葉とイメージがむすびつきやすくなり、頭の中で想像する力を助けます
言葉とイメージがむすびつきやすくなり、頭の中で想像する力を助けます